マルチバイブレータ回路で方形波を発振します。
(1)評価回路
方形波を発振するマルチバイブレータ回路を図22-1に示します。
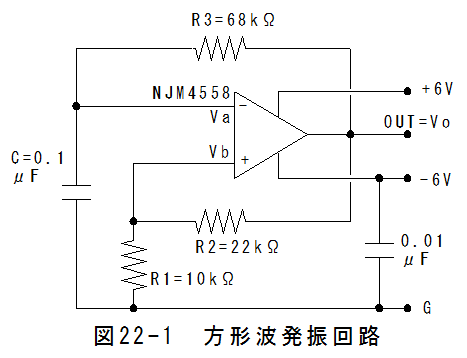
マルチバイブレータ回路は図22-2に示すヒステリスコンパレータとCRの充電・放電回路で構成されます。
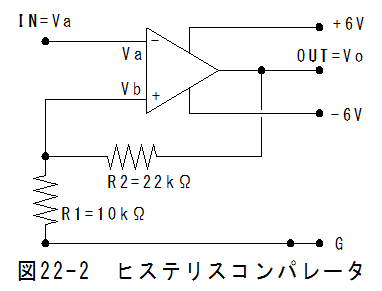
図22-2において、Vb > Vaの時、
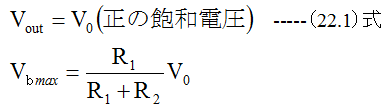
図22-2において、Vb < Vaの時、
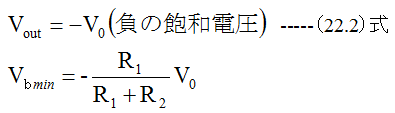
基準電圧Vbが変化することにより、ヒステリシスが発生することになります。また、Voutが正のとき、コンデンサは充電され、Voutが負のとき放電されます。
CRの充電・放電回路の充電状況により、比較電圧Vaが変化します。比較電圧VaがVbminより小さくなりと充電が開始され、VaがVbmaxより大きくなると放電が開始されます。
充電・放電が周期的にくりかえされることにより、方形波を発振します。
CR回路の充電・放電時間を与える式は「3章:コンデンサ容量測定」のコンデンサCの両端の電圧Vcを与える(3.7)式となります。
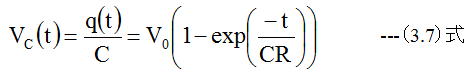
ただし、マルチバイブレータ回路では±Voであるため、(3.7)式は以下のようになります。
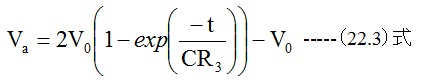
充電開始時間t1は(22.1)式、(22.2)式、(22.3)式から
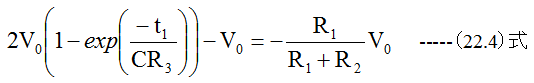
同様に放電開始時間t2は
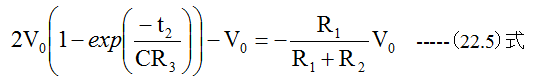
この回路では、充電時間と放電時間は同じであり、周期Tは
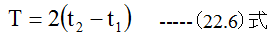
(22.5)式に(22.4)式と(22.5)式を代入して整理すると
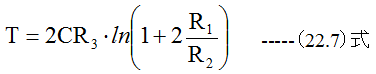
従って、発振周波数fは
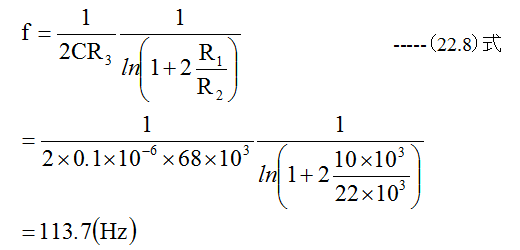
となります。
図22-1のマルチバイブレータ回路の出力波形を簡易オシロで観察した結果を図22-3に示します。
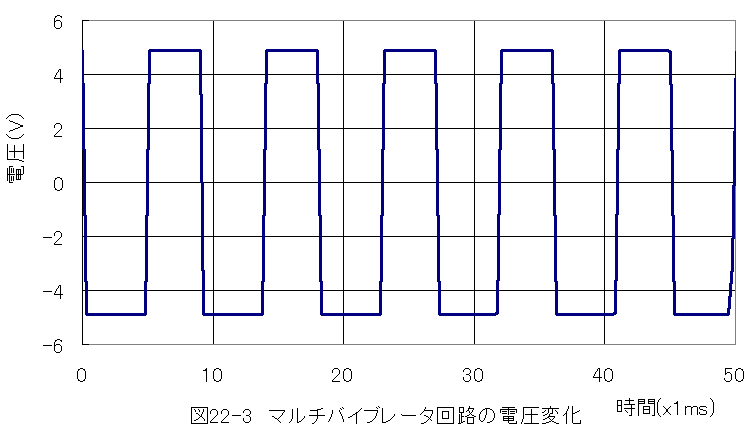
図21-3の出力電圧変化において
・波形振幅:±4.9V
・発振周期:9ms(充電4.2ms、放電4.8ms)
・周波数f:111.1Hz
となり、計算値113.7Hzと近い値となる。
(1)マルチバイブレータ回路により、方形波出力波形を得ることができる。
(2)周波数は計算値113.7Hzに対して実測値111.1Hzと近い値となる。
(3)理論的には、充電時間と放電時間は一致するはずであるが、実測値では充電時間と放電時間は差が生じる。
(4)簡易オシロは測定間隔の制限から、500Hz以上の高周波波形の観察は適さない。
(5)マルチバイブレータ回路は500Hz以下の低周波方形波形を得ることができる。
(6)簡易オシロの測定可能電圧範囲が0〜5Vであり、オペアンプ出力範囲±6Vをカバーできない。
(7)簡易オシロの測定可能電圧範囲が0〜5Vに収めるため、抵抗分圧を行う必要がある。